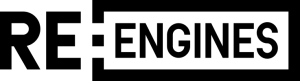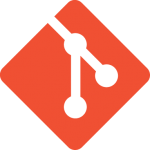はじめに
今回は、VSCodeでCopilot Agentをより活用するために、MCPについて調べました。
VSCodeでのMCP Serverの設定
他のツールと同じように、
mcp.json
で定義することで、Agentモード利用時にMCPを使うことができます。VSCodeでの設定方法を紹介します。
グローバルとワークスペース
VSCodeでは
mcp.json
を「グローバル用」と「ワークスペース用」と使い分けることができます。
- グローバルに配置する場合は
~/Library/Application Support/Code/User/mcp.jsonに書きます。 - ワークスペースに配置する場合は、ワークスペース配下の
.vscode/mcp.jsonに書きます。
MCP Serverの追加
mcp.json
を定義することでMCP Serverを追加することができますが、VSCodeでおすすめのMCPを紹介している「Discover and install MCP Servers in VSCode」というページでは、VSCodeで簡単にインストールできるMCPがまとめられています。
ここからインストールすると、
mcp.json
に自動的に追加されます。
例えば、今回紹介する playwright と Context7 を追加すると、以下のようになります。
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | { "servers": { "playwright": { "command": "npx", "args": [ "@playwright/mcp@latest", "--isolated" ], "type": "stdio" }, "context7": { "command": "npx", "args": [ "-y", "@upstash/context7-mcp@latest" ], "type": "stdio" }, }, "inputs": [] } |
playwrightのargsに
--isolated
を渡すことで、cookieなどを永続しないようにしています。こうすることで、毎回まっさらなところからスタートできるので、ログイン処理などを毎回初めから実行できるようになります。
今回は、MUIのCRUDテンプレートプロジェクトをお題とし、MCP Serverを使ってみたいと思います。
ユースケース1: Playwright MCPでテストコード生成
Playwright MCPを使うと、自然言語によって Playwright を操作することができ、対話しながらさまざまなWebページを取得・操作することができます。
今回はローカルで立ち上げたReactアプリを実際に分析してもらい、Playwrightのテストコードを書いてもらいます。
まずは、プロンプトです。
これから Playwright MCP を使ってブラウザを操作します。
あなたは、Playwrightテストコードを作成するエージェントです。
以下のルールに従ってテストコードを生成してください。
– Playwright MCP を使うことは何があっても絶対に忘れないでください
– 必ず Playwright MCP を使用して、1ステップずつ処理し、その都度@playwright を利用して、TypeScript形式のテストコードを追記してください。
– Playwright MCPを使わず、シナリオを一括でコード化してはいけません。
– 生成するテストはtests/tmp/one.spec.tsのtest("E2Eテスト", async ({ page, context }) => {});の中に追記してください。シナリオ
1. Playwright MCP を使って「http://localhost:5173」を表示する
2. 「Create」ボタンを押す
3. Nameに任意の文字を入力する
4. Ageに任意の数値を入力する
5. Join dateに任意の日付を入力する
6. Departmentに任意の部署を1つ選択する
7. 「Create」ボタンを押す
8. 新規作成した従業員が一覧に追加されていることを確認する
いろいろと試行錯誤してこのプロンプトになりました。GPT-4.1でうまく動いています。(GPT-5でも動くと思いますが、時間がかかります。)
ポイントをまとめます。
- 会話履歴の要約をオフにする
コンテキストが膨れ上がってくると、Copilotが会話履歴の要約をします。しかし、要約後は最初の指示を忘れてしまい、うまくテストの作成ができなくなってしまいます。
そこで、VSCodeの設定でgithub.copilot.chat.summarizeAgentConversationHistory.enabledをオフにすることで、会話の要約機能をオフにすることができます。 - プロンプトの冒頭で「これから Playwright MCP を使ってブラウザを操作します。」を書く
これを書かないと、Playwright MCPを使用せず、推測でテストコードを書いてしまうことがあり、挙動が不安定になりました。 - プロンプトにテストケースを書く
テストケースを書かないと、毎回違ったテストケースとなってしまい、安定しません。テストケースは明示したほうが精度よくテストケースが出てきます。
このプロンプトを実行すると、大まかに問題のないテストコードが生成されますが、実際に実行してみると動かない点がいくつか出てきますが、これをAgentに修正させるのは今のところ難しかったため、これは手作業で修正します。
ユースケース2: Context7 MCPで最新ドキュメントを参照
Context 7 MCPを使うと、さまざまな最新ドキュメントをRAGとして使用できるようになります。その数は膨大で、ReactやTailwind、FastAPIなどはもちろん、MUIやGolangなど、実にさまざまなドキュメントを参照できるようになります。
ドキュメントの対応状況は公式サイトにまとめられています。
使い方は、プロンプトに
use context7
と足すと context 7が質問やソースコードをもとに適切なドキュメントを探し、それを参照しながら回答してくれます。
例えば、以下のようなプロンプトになります。
React 19に対応していない箇所がないか調べて use context7
そうすると、以下のような回答が得られます。
React 19の主な非互換・移行ポイント(context7公式情報より):
– <Context.Provider>の代わりに<Context>を直接Providerとして使う新構文が導入され、旧構文は非推奨(ただし自動変換codemodあり)。
– レガシーContext API(contextTypes/getChildContext)は完全削除。React.createContext/ useContext/ contextType への移行必須。
– useContextは引き続き有効だが、React 19では新たにuse(…) APIが追加され、条件付きでContext値を取得できる(useContextは条件分岐内で使えない)。
– PropTypes, defaultProps(関数コンポーネント)は無視される。TypeScript型推奨。
– ReactDOM.render, ReactDOM.unmountComponentAtNode, createFactory, string ref などは削除。createRoot, root.unmount, JSX, ref callbackへ移行。
– ref callbackでreturn値を返すとTypeScriptエラーになる(returnせずブロックで書く)。
– useSyncExternalStore, useEffect, Suspense, Server Componentsなどは引き続き利用可能(APIの大きな破壊的変更なし)。**workspace内のコード調査結果:**
– レガシーContext API(contextTypes/getChildContext)は未使用。
– <Context.Provider>構文は使われている可能性があるため、<Context>構文への移行を検討。
– useContext, useEffect, useSyncExternalStore, Suspenseは通常通り使われている。
– PropTypes, defaultProps, string ref, createFactory, レガシーライフサイクル(componentWillMount等)は見当たりません。
– ReactDOM.renderは使われておらず、createRootが使われている(index.tsx)。**結論:**
– 重大なReact 19非対応箇所は現状見当たりません。
– <Context.Provider>→<Context>への書き換え(新構文)を検討するとよりReact 19らしいコードになります。
– 公式codemod(npx codemod@latest react/19/migration-recipe)で自動変換も可能です。他に特定のファイルやAPIについて追加で調査したい場合は教えてください。
確かに、今回のプロジェクトでは
useContext
や
Context.Provider
が未だに使われていて、この指摘は正しいと言えます。
こちらは、GPT-4.1で問題なく使えました。
ちなみに、
use context7
せずに依頼すると、これらの指摘はされませんでしたので、最新情報を参照させたいときはかなり使えそうです。
また、ブラウザでドキュメントを探さなくても、IDE上で確認できるので、これは便利に使えそうです。
さいごに
今後は、複数のMCPを組み合わせて活用する方法についても調べてみたいと思います。